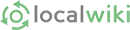「南部」と書いて「みなべ」と読む土地は私たちの南部町だけで他の地方は「なんぶ」と読んでいる。
2004年(平成16年)10月1日、南部町と南部川村が合併し「みなべ町」が発足。
「南部」という地名の由来にはいくつかの諸説がある
1.開化天皇の皇子の所領説
『古事記』の開化天皇の条「建豊波豆羅和気王は、道守臣、忍海部造(大和国忍部群)、御名部造、稲羽(因幡国)の忍海部、丹波の竹野別、依網(河内国円比群)の阿毘古(姓のこと)の祖なり。天皇の御年、六拾参歳」と記している。このなかの「御名部」については小学館発行の『日本古典文学全集』では私たちの南部町としている。
2.舒明天皇(有間皇子の祖父)の皇女御名部皇女の所領説
『皇胤系図』によると舒明天皇と石川麿大臣の女姪娘との間に御名部皇女がある。この皇女が南部の土地を所領されていたから、皇女の名前をとって「御名部」と称するようになり、後に「南部」となったという。
ところが、御名部皇女は舒明天皇の御子の天智天皇にもあり、母も同じ石川麿大臣女姪娘となっている。一般的にこの『皇胤系図』の舒明天皇の皇女説は間違いとされている。
3.天智天皇の皇女御名部皇女の所領説
『皇朝皇胤紹運録』や『皇代記』に、天智天皇と石川麿大臣女姪娘との間に御名部皇女がある。この皇女が南部の土地を所領していたから、皇女の名前をとって「みなべ」と称するようになったという。御名部皇女について『大日本史』にも「御名部内親王嬪姪の所生なり。慶雲元年(七〇四)封一百戸を益さる。阿部(阿閉)皇女御名部内親王の同母妹にして、是を元明天皇となす」と記されている。この皇女は和歌をたしなまれた方で『万葉集』に わが大君ものな思ほし皇神 嗣ぎて賜へる吾無けなくに という歌がある。 この御名部の土地はどこであるかについては先きに記したとおりであるが、『万葉集』巻九大宝元年(七〇一)太上天皇、大行天皇紀伊国に幸しし歌に、 三名部の浦塩なみちそね鹿島なる 釣する海人をみて帰り来む という歌がある。太上天皇とは(現在)の天皇すなわち文武天皇であり、大行天皇とは先き(退位された)の天皇すなわち元明天皇の姉の持統天皇である。この歌の「三名部」の土地は私たちの「南部」であることに間違いはない。
4.「鹿島」の三鍋説
先に記した『万葉集』巻九に詠まれている「鹿島」の名前の起源は、鹿が住んでいたからとも、鹿島に鎮座の「タケミカヅチノミコト」は茨城県の鹿嶋神宮から勧請したからともいう。この鹿島は大昔から南部の町を津波や大波から守る自然の防波堤の役目を果たしてきたと同時に南部の象徴的な存在でもある。この鹿島を南道方面から見ると、三つの島からできているように見え、それがちょうど鍋を三つ伏せたような形がしているから、三ッの鍋すなわち三鍋(みなべ)と呼ぶようになり、それがこの地方全体の名前となったという。この「三鍋」という文字が文献に初めて見えるのは新しく、平安時代末の承安四年(一一七四)藤原経房の日記『吉記』で、「三鍋海福寺」と記している。なお、現在も北道の王子社は「三鍋王子社」と記すのが正式な書き方である。
5.「岩神さん」の三鍋説
南部川村筋の超世寺の東方約一五〇㍍の水田の畔に、径四〇㌢㍍前後の三個の石が並んでいる。この石を土地の人々は「岩神(いわがみ)さん」と呼び、正月にはシメ縄をはり餅・串柿・みかんを供えている。この岩神さんについて次のような伝説がある。
いつのころであったか、とにかく遠い昔のことである。ある静かな秋の夜であった。にわかに天の一角から金の矢が三本降ってきたかと思うと、大きな地ひびきがして三個の石が、田圃のまん中へ落ちてきた。「天からござった石だ、天の神様に違いない」というわけで、村人たちはしめ縄をめぐらし、御酒を供え、「岩神さん」と名付け、今にあがめまつっている。この石は色のまっ黒なところ、少し長めではあるが、まん丸いところが、農家の家で使う鍋の尻にそっくりであるところから、いつだれがいい出したともなく三鍋(みなべ)と呼ばれ、おしまいには土地の名前になったという(『日高民話伝説集』より)。
6.「底なし沼」の三鍋伝説
「岩神さん」の約三〇〇㍍北に、南部川跡にできた底なし沼がある。その沼底にさきの岩神さんと同じように天から落ちてきたという石が三つあり、それがちょうど鍋の大きさで形もよく似ていることから「三鍋(さんなべ)」と呼ぶようになり、更に「三鍋(みなべ)」と変わり、この土地の名前となったという(『随筆みなべ』)
7.「海辺(みのべ)」の意味説
吉田茂樹著の『日本地名語源辞典』に、南部町は万葉集「(第一六六九)」大宝元年(七〇一)にみえる三名部の浦に由来し、「ミノベ(海辺)」の意であると記されている。
8.「水辺」の意味説
「海辺」とほとんど変わりはないが、「水辺(みずべ)」を「水辺(みなべ)」と呼んでいる土地は奈良県をはじめいくつかある。どの土地も池・沼・川に面したところであることから、南部も「水辺(みずべ)」なる語が転じたものではないかとも考えられる。
9.「ナベラ」・「ナメラ」の説
鏡味完三の『日本地名学』などに、①山の広いゆるい傾斜地に細流のある土地とか、②谷に露出した岩の平面広く滑らかな所を「ナベラ」と呼び、①土なく岩ばかりの所とか②一枚岩の滑らかな地形を「ナメラ」という。「南部」も「岩代」の地名のように「ナメラ」・「ナベラ」からきたのではないかとも考えられる。
10.日高郡の南部(なんぶ)説
『紀伊続風土記』に「南部の名万葉集に三名部の浦とあり其名の古き事知るへし。名義を考ふるに日高郡の内にて最南にあるを以て称するならむ、古事記の開化御巻に御名部造といふ姓見えたり書記の欽明御巻に佐渡ノ島ノ北御名部之崎といふも見えたり」と記している。
『南部史より引用』