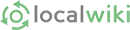紀州備長炭は均一に熱・赤外線・こうばしさを伝えることができるという特長を持っている。普通の備長炭は炭素濃度85%程度である。一方、紀州備長炭は精錬(ねらし)という、工程を経て特長が生まれている。備長炭は、別名白炭と呼ばれ、窯から出して消火時にかけた素炭が残り、それが白くなっているのでそう呼ばれる。
昭和三十年頃、もともと炭だった家庭燃料が一気にガスになる。その結果、炭が必要となれなくなり、木材も必要なくなって売れなくなる。
高度成長期には、山のバブルが起こる。備長炭の原料であるウバメガシに対し、スギヒノキは1年で育ち高値で売れる。そのため、みなべ町も半分がこれらになった。そのような苦しい状況の中で、みなべ町民はウメを作り耐え忍んだ。
バブル期には、備長炭が有名になり、梅農家から多くの人が転職した。特に冷夏だった年には、日本でコメが十分に取れなかったことから、多くの外国産米が輸入された。その結果、それらのコメをおいしく炊く方法として備長炭が重宝され有名になった。
現在では、備長炭の生産者の減少によって生産量も減少している。また、高値で売れるからといって木を多く切った過去のつけも回ってきている。一方、しっかりとやればもうかる仕事であることも事実であり、Iターン者も増えてきている。しかし、択伐をして森を守ったりという本質的なことをしないものも多く、問題になっている。炭焼き師の原さんは、Iターンもいいができれば地元みなべ町出身の人が後を継いでいってくれると嬉しいという感想を述べていた。